2016年01月22日
スポンサーリンク

初めて憂歌団を見たのは、名古屋の千種にある理容会館という場所であった。普段は何に使っているのか判らないが、広いホールに簡単な照明装置を持ち込んだような会場で、床にゴザを敷き、観客はそこに座り込んでライヴを楽しむ。煙草の煙がたちこめ、誰が持ち込んだのか一升瓶の回し飲みが始まる。こんな光景も70年代初頭ならではのものだ。
このブルース・コンサートには、すでに人気が出始めていたウェストロード・ブルース・バンド、オールマン・ブラザース・バンドのフィルモア・ライヴをそのまま再現していた合資会社、京都出身のフォーク・シンガー豊田勇造、日本人離れした入道のヴォーカルをフィーチャーしたブルース・ハウス・ブルース・バンドなどが出演していた。このライヴに飛び入りゲストのような形で出演したのが、内田勘太郎と木村秀勝(現在は充揮)の二人組であった。
会場の後ろから観客をぬって舞台に登場し、少し照れくさそうに演奏を始めた。内田は今のような短髪ではなく、ぞろりと肩までの長い髪、木村は痩せこけていて少年のあどけなさを残していた。出てきた音は強烈だった。木村のドス黒くしゃがれた声に、内田のスライド・ギターが執拗に絡んでいく。
ジャズ・ジラム「キー・トウ・ザ・ハイウェイ」や、タンパ・レッドの「キングフィッシュ・ブルース」などを歌ったと記憶する。ソーニー・ボーイ・ウィリアムソンの「グッド・モーニング・リトル・スクールガール」を日本語で「ちょいとそこ行くネーチャン」と訳して歌っていたのが強く印象に残っている。これらの曲は、ビクターから発売になっていた戦前ブルースの集大成アルバム『ブルースの古典』に収められていた。戦前のカントリー・ブルースが大好きで、好きが高じて自分たちも歌い始めてしまった。そんな初々しさと熱さを感じさせるステージであった。
すでにこの頃から日本語のブルースを歌っていたことに驚かされてしまうが、憂歌団が日本語で歌い出したのには、ひとつの出会いがある。同じようにブルースに目ざめ名古屋で活動していた尾関ブラザーズとの出会いだ。彼らは名曲「シカゴ・バウンド」の作者であり、他にも「金持ちのオッサン」「俺の村では俺も人気者」といった初期の重要なレパートリーを提供している。尾関ブラザーズについては書きたいこともあるのだが、それはまたの機会に。
憂歌団がアルバム『憂歌団』をひっさげてデビューしたのは、それから少し経ってからの事だ。そのブルースの咀嚼ぶり、痛快なまでの諧謔性に仰天し、心からの喝采を送ったものだ。ここから彼らの輝かしい歴史が始まっていったのだが、憂歌団が憂歌団になるまでの過程が知りたければ、2000年に発掘CD化された未発表音源集『LOST TAPES』をお薦めする。ここにはブルースに対する熱意と愛情が存分に詰まっている。
木村充揮と共に憂歌団を築きあげたギタリストの内田勘太郎は、本日(1月22日)に誕生日を迎えた。彼のブルースを支えた愛器チャキとともに、この日を祝っているかと思う。

憂歌団「LOST TAPES 」

生聞59分 (紙ジャケット仕様
関連記事
-

1975年4月1日、ウエスト・ロード・ブルース・バンドがアルバム『Blues Power』でバーボン・レーベルからデビュー
1970年代初頭から中頃にかけて日本のロック・シーンを席捲したものに“ブルース・ブーム”があるが、そのブームを生み出したのは主に関西のブルース・バンド勢だった。そんなことから“関西ブルース・ブー...
-

1979年10月8日、桑名正博「セクシャルバイオレットNo.1」がオリコン1位を獲得~「セクシャルバイオレットNo.1」制作秘話
RCAビクターの小杉理宇造ディレクターが走り回ってくれて、7月にリリースする桑名正博のシングル盤が、カネボウ化粧品のキャンペーン・ソングに決まった。前年ヒットした、矢沢永吉の「時間よ止まれ」(資...
-

パチンコといえば憂歌団、そして木村充揮の絶叫によって日本語のブルースは幕をあけた
11月14日は「パチンコの日」だそうだ。<パチンコ>と聞いて真っ先に思い出すのが憂歌団だ。「パチンコ」を最初に聴いた時には、大袈裟じゃなく椅子から転げ落ちた。こんな衝撃的な体験は初めてだった。 ...
-
40年前の本日、上田正樹&サウス・トゥ・サウスの名盤『この熱い魂を伝えたいんや』がリリース
上田正樹&サウス・トゥ・サウスとしての初アルバム『この熱い魂を伝えたいんや』が発売されたのは1975年12月15日。当時としては考えられない、掟て破りのライヴ・アルバムでのデビューであった。 t...
-
桑名正博のファニカン時代
今日、10月26日で、桑名正博が逝って3年がたつ。43年前の当時、700坪はあろうかという桑名の実家にある倉庫で寝泊まりして、ファーストアルバム「Funny Company」を全曲作り上げた。そ...
-
今日は、仲井戸“CHABO”麗市の65歳の誕生日!
本日10月9日は仲井戸“CHABO”麗市の誕生日。65歳となる。古井戸でデビューしてから45年が経過した。古井戸の時代はステージ上で一言も発せず、黙々とギターの弾いていたチャボだが、今ではテレビ...
-

1973年、横浜にも野外音楽堂があった。そこで聴いたのはピッカピカの、まだ3人だったRCサクセションとチャボのいた古井戸だった。
かわいいルックスのRCはフォーク界の中でもアイドル寄りだと思っていた私は、初めてのRCのライブで考えを改める。ハードなギターのリズムが醸し出す男っぽいグルーヴあるサウンドは初めて聴く音楽だった。
-

「ヤング720」にアマチュアの高校生であったRCサクセションが登場
「ヤング720」にアマチュアの高校生であったRCサクセションが登場。後にデビュー・シングルのB面となる「どろだらけの海」
-
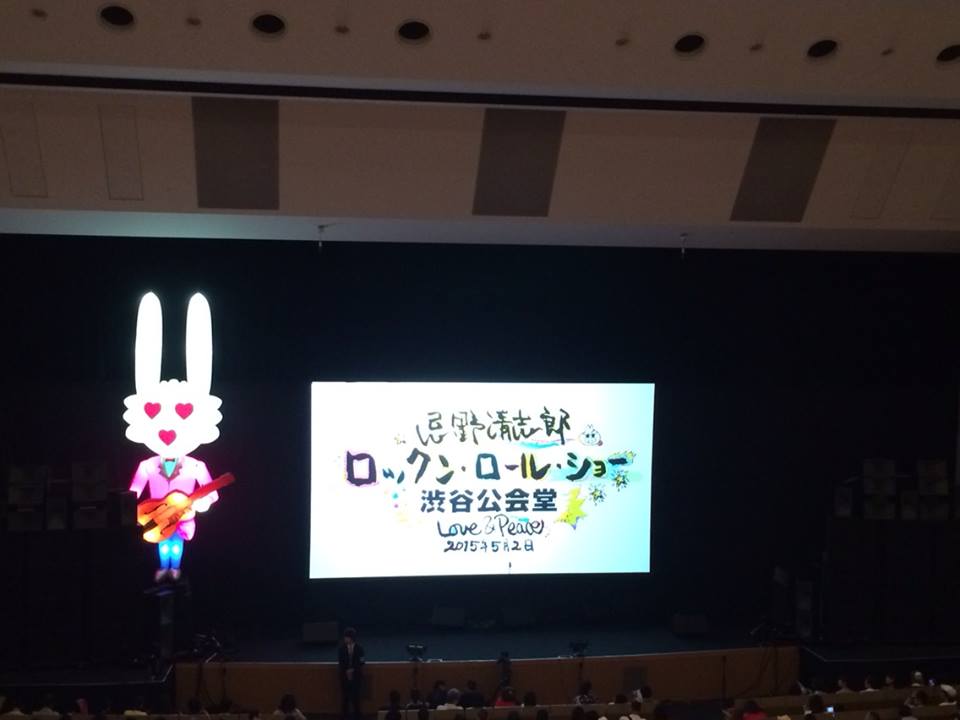
5月2日。忌野清志郎が逝ってから6年になる
5月2日。忌野清志郎が逝ってから6年になる。時は瞬く間に過ぎ去り、世の中は驚く程変わった。 海の向こうでは戦争が止むどころか、ますますその戦火の渦は拡大している。東日本大震災の被災者達はいまだ家...













